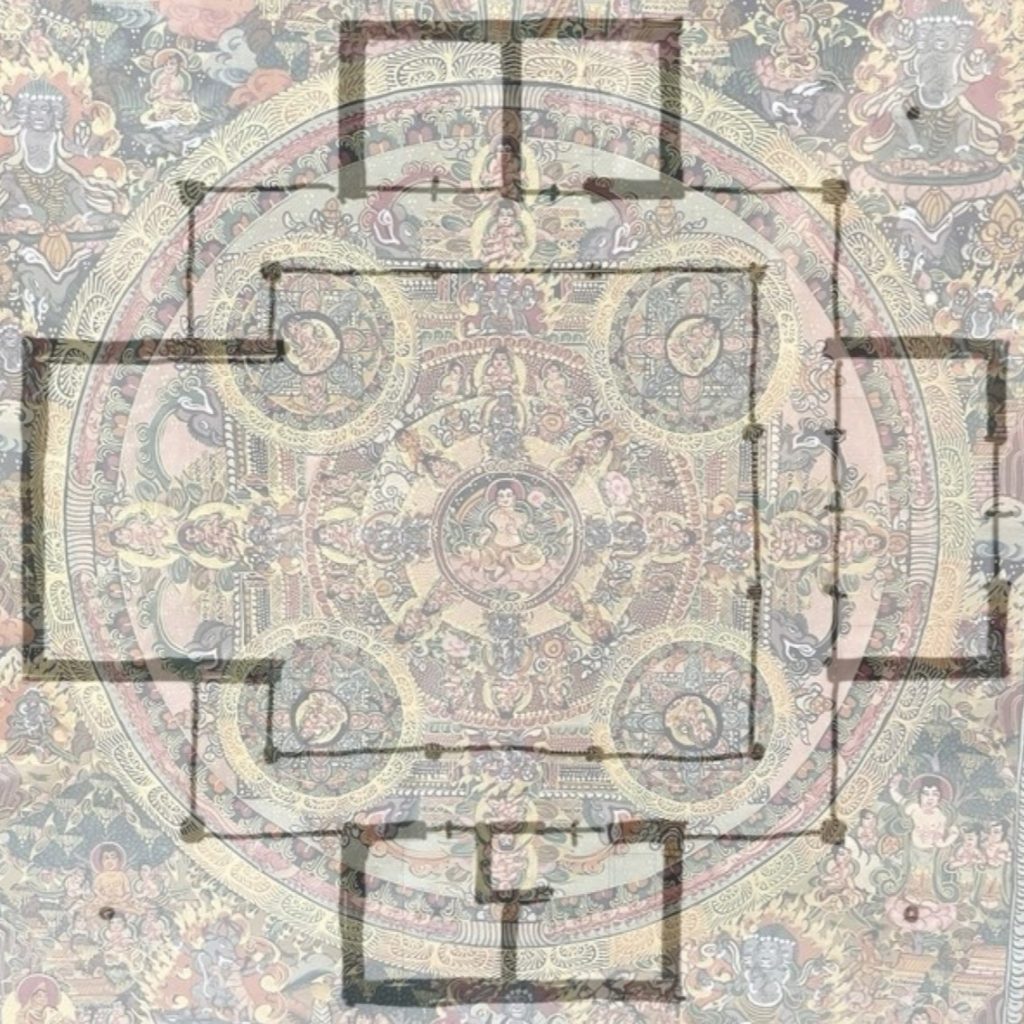江田島での打合せの帰り
高速道路が通行止めになっていた.
やむなく海沿いの道を走り
途中で竹原に立ち寄る.
思いがけない寄り道だったが
その静けさはどこか必然のようにも感じられた.
竹原と倉敷を歩くと
町並みとは建築の集合ではなく
時間が設計した都市空間であることに気づく.
竹原は塩づくりの営みから生まれた商人の町だ.
暮らしの延長として建築が建ち
その連なりが静かに残った.
軒の高さ、瓦の光
格子の奥の気配までが穏やかに揃い
町全体がひとつの建築のように感じられる.
そこにあるのは「住むための美」
語りすぎず、整えすぎない余白が
空間に深さを与えている.
一方、倉敷は物流が骨格をつくった都市である.
運河に沿って白壁の蔵が並び
視線は遠くへ抜ける.
構成の意志がはっきりとした
見せるための風景だ.
倉敷が「構成の美」だとすれば
竹原は「余白の美」
都市デザインとして完成された倉敷.
時間が静かに沈殿した竹原.
建築の強さとは形の新しさではなく
時間の中でなお静けさを
保てることなのかもしれない.