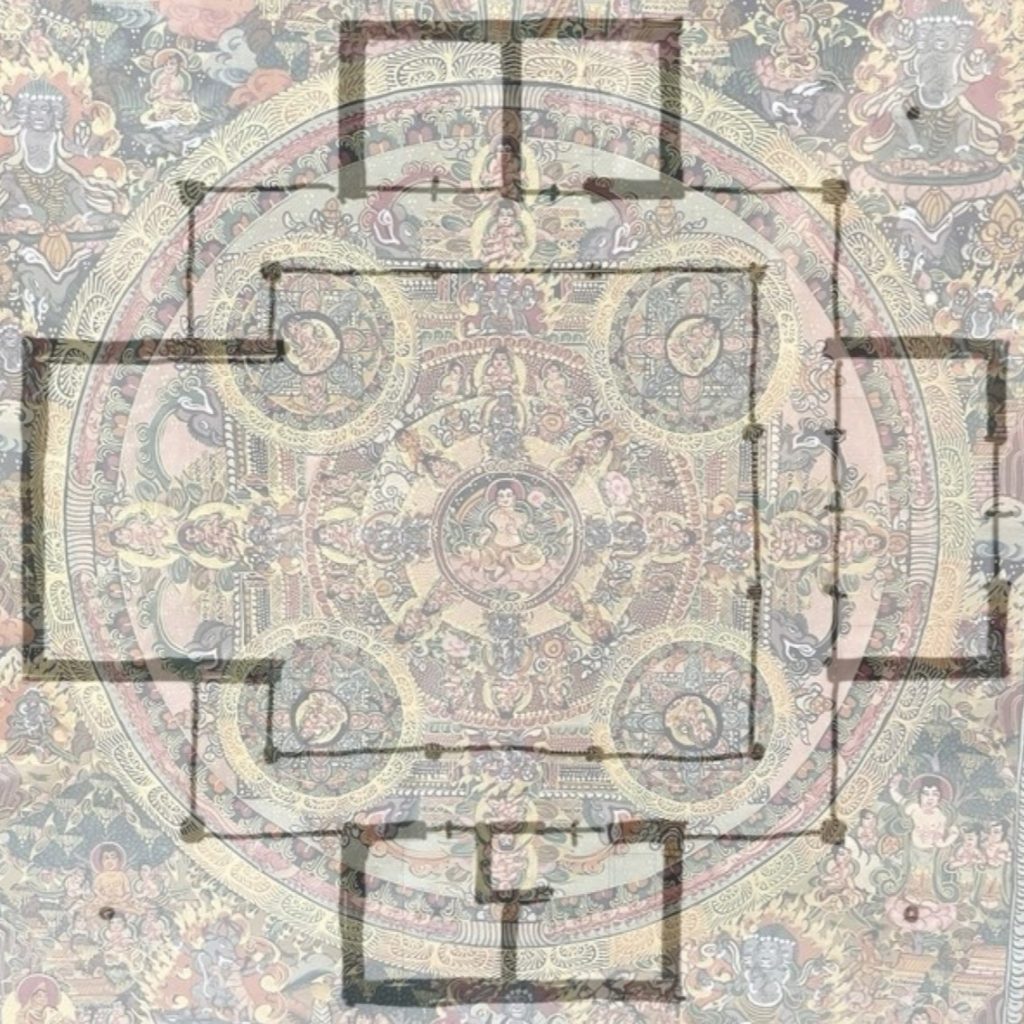:
一年の終わりは
建築にとって「区切り」というより
静かに堆積した時間を見つめ直す季節のように思います.
:
現場で交わした何気ない会話
図面の線を一本引き直した夜
光が思ったより深く差し込んだ朝.
そうした一つひとつが
建築の輪郭を少しずつ確かにしていきました.
:
建築は完成した瞬間だけが答えではなく
むしろ迷い立ち止まり
選ばなかった道も含めて
その建物の「時間」になるものだと感じています.
:
今年もまた土地に耳を澄まし
人の暮らしの速度に合わせて
無理のない形を探し続けた一年でした.
整えすぎず
語りすぎず
それでも確かに息づく空間を目指して.
:
関わってくださった施主の方々
職人の皆さん
同じ現場に立ってくれたすべての人に
心から感謝いたします.
:
年が改まれば
また新しい条件
新しい風土
新しい対話が待っています.
急がず焦らず
建築が自然に立ち上がる瞬間を信じて
来年も一つひとつ積み重ねていきたいと思います.
:
本年もありがとうございました.
どうぞ穏やかな年の瀬をお過ごしください.
:
雪に包まれた記憶.
2月の白川郷にて.